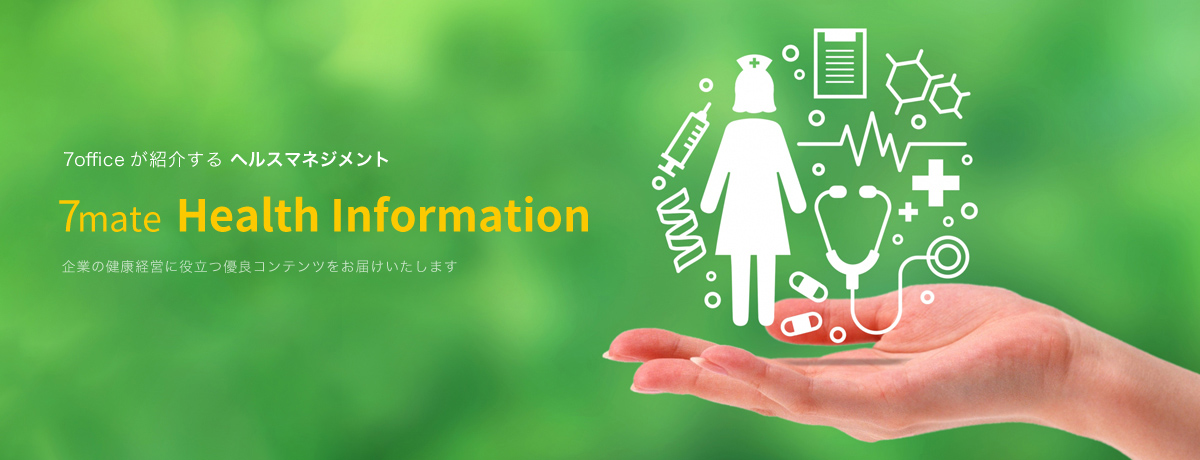第6回 アンガーマネジメント
皆さんは仕事や日常でイライラしたり、腹が立ったりすることはありませんか。価値観が多様化している現代では、お互いの価値観が認められないことで対立したり、トラブルになったりするケースが増えています。職場でのパワハラ、駅員への暴行、家庭内DV、学校でのいじめや体罰、大相撲力士の傷害事件、自動車のあおり運転のトラブル、等々数えればきりがありません。これらは怒りの感情がもたらしたともいえるかもしれません。
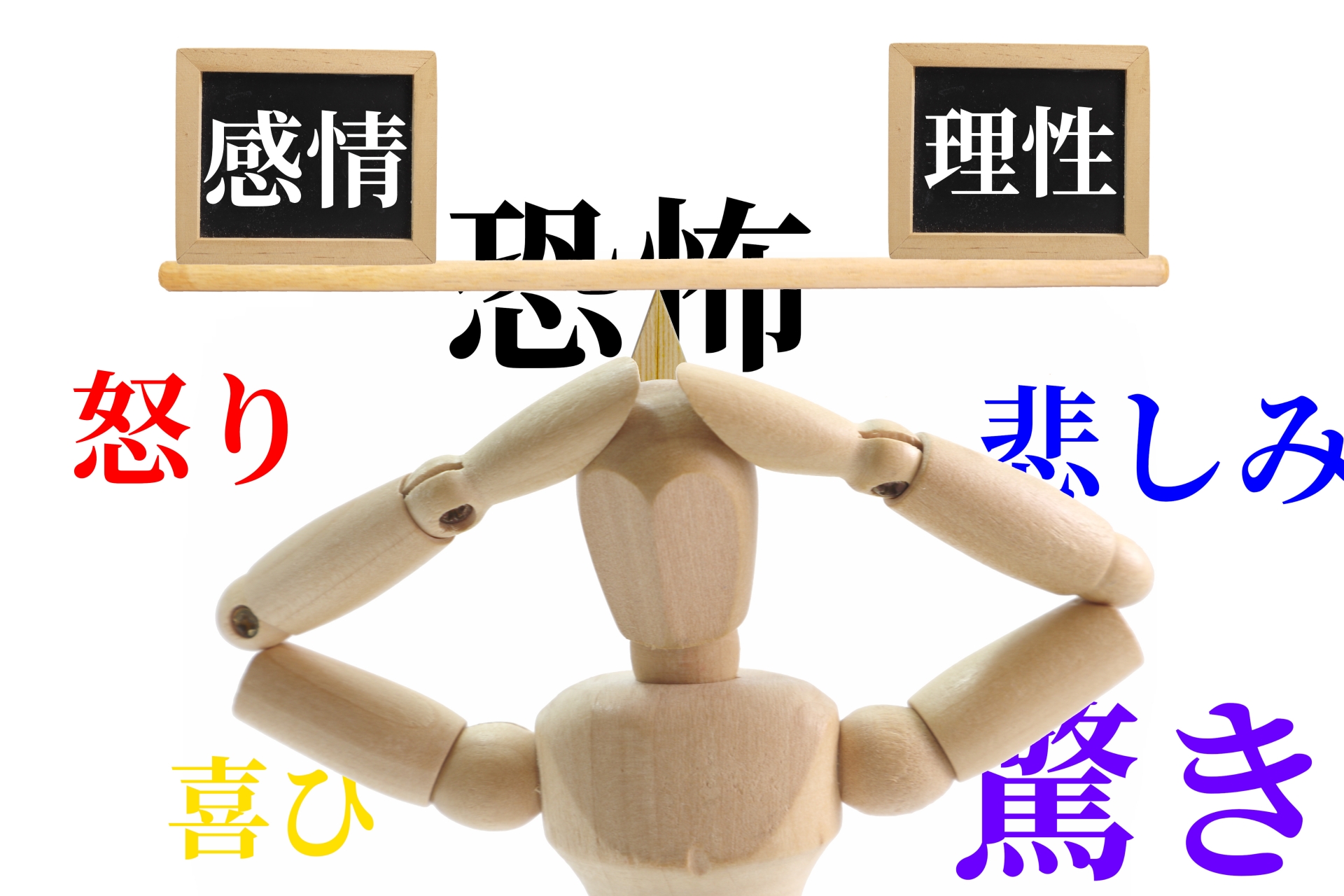
アンガーマネジメント
アンガーマネジメントは、このようなストレスに伴う「怒りの感情」や「行動」の背景にある認知に焦点を当て、自らの力で感情をコントロールできるようになることを目指した認知心理学の理論に基づいた方法です。
アンガーマネジメントでは怒ること自体は悪いことしてはいません。そもそも怒りとは私たちの身を守る大切な感情の一つだからです。アメリカの学者によって提唱されたものに動物の恐怖への反応で、「闘争・逃走反応」があります。これは危機や恐怖が差し迫ったとき、戦うか逃げるかとっさに判断して対応できる状態を作り出すことですが、人間も危機が迫ると、消化吸収や、体力回復に使うためのエネルギーを大腿筋や上腕筋などの大きな筋肉に回し、とっさの動作にも反応出来るように体を準備します。この時に使われるのが怒りの感情だといわれています。
アンガーマネジメントでは怒らなくなることではなく、怒る必要があるときは上手に怒れ、必要のないときは怒らなくて済むようになりましょうということを目指します。
アンガーマネジメントは手法であり、だれでも訓練すれば習得・習慣化できるものです。このことを理解してアンガーマネジメントを実践していきましょう。衝動、思考、行動をコントロールすることがポイントになります。

まず第一は衝動的に反射しないことです。例えば、朝の通勤の満員電車で言い合いや小競り合いのケースに出くわすことがありませんか。きっかけはちょっと足を踏まれたとか肘が当たったといった程度のもので、やり返したり、謝れと言ってもめたりするトラブルです。この時にすぐにカッとしてやり返したり、言い返したりしないことが大事です。怒りのピークは数秒といわれていますが、この数秒間に衝動的に反射しないことが重要なのです。そのためには、ひと呼吸つく、心の中で「大丈夫」とか「落ち着け」といった言葉をつぶやくことで怒りのピークをやり過ごし、少し冷静になって大きなトラブルになることを防ぎます。アンガーマネジメントでは怒りのピークをやりすごす方法は他にもいろいろありますが、色々覚えるのではなく、一つでいいので、いざというときに自分が自然に使えるものを習得しましょう。
また、怒りは突然沸き上がってくるものではなく、「不安」、「痛い」、「疲れた」、「寂しい」、「いやだ」といったネガティブな感情が私たちの中で膨れ上がって心のキャパシティーを超えたときに怒りの感情につながると言われています。つまり怒りとは第2次感情なのです。先ほどの通勤電車のケースではちょっとしたことで反射してしまう例を取り上げましたが、昨日上司に怒られたとか家で奥さんと喧嘩したとか様々なネガティブ感情が蓄積されているとちょっとしたことで、キャパシティーを超えてしまい、衝動的に反射してしまうのです。これを防ぐにはネガティブな感情をため込まないことも必要ですが、心のキャパシティーを大きくしていくことも必要です。

心のキャパシティーを大きくするには、その人が持っている思考(物事の考え方、捉え方、価値観など)を知ることが重要です。あなたにとって自分を怒らせる原因は何だと思いますか。それは誰かでしょうか、それとも何かの出来事でしょうか。実は誰かや出来事ではなく自分の思考に原因があるということです。自分の持っている思考、コアビリーフ(こうあるべきという思い)が目の前の現実と相いれないときに怒りの感情につながります。
職場で部下から上司に対して挨拶や報連相ができていないとか電車を待っている列に割り込んではいけないといった仕事上のあり方やマナーやルールは守るべきといったものまでさまざまなものがあります。
厄介なのは、信じているコアビリーフが人それぞれ違うということです。その人にとっては正解でも他の人ではそうでなかったり、程度が違ったりすることです。例えば会議の時間は守るべきだと考えている人達がいたときに、少なくとも5分前には会議室にいるべきという人もいれば時間ちょうどにいればいいという人もいます。お互いに思っている程度が違えば、人間関係にも影響が出るかもしれません。それではこのコアビリーフとどう付き合っていけばいいのでしょうか。自分の中で許せる領域、まあ許せる領域(ここまでが許容範囲)、許せない領域があったときに私たちが怒るのは許せない領域にあるものです。それ以外は怒る必要がないのです。怒ってしまった後によく考えると怒る必要はなかったなと後悔する場合はそれが許容範囲であったのかもしれません。必要なことには怒れて、必要のないことには怒らなくなるには、この許容範囲と許せない範囲の境界線を意識することと許容範囲をできるだけ広げてあげて、許せない範囲を減らしてあげることです。無理に広げる必要はないですが、できるだけ広げてあげたら境界線を安定化させることも必要です。その時々の機嫌で境界線を変えてしまうと周りが混乱します。そして境界線を安定させることに加えて、開示することも意識しましょう。
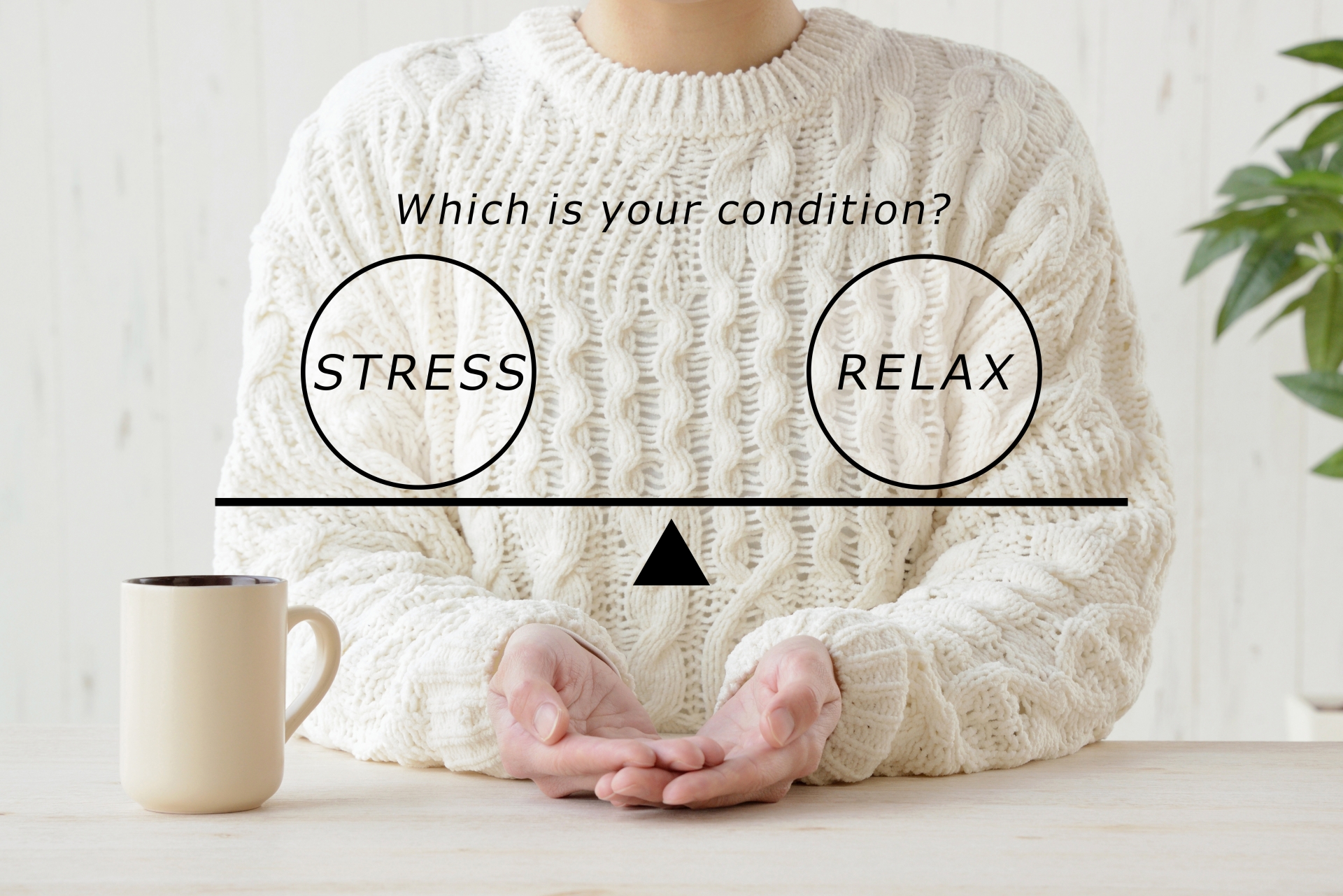
最後はコントロールできるものとそうでないものを区別して対処するというものです。例えば、悪天候や高速道路の渋滞など自分では変えることはできないことにイライラしたりしたことはありませんか。これはコントロールできないものをしようとしてイライラしているのです。コントロールできないものはまずは現実を受け止たうえで別の対処法を実践することです。雨が降ったら傘をさし、渋滞だったら音楽を聴いたり、誰かがいれば話をしたりして気分を変えます。変えられるものを変えようとしないということです。過去と他人は変えられないといいます。アンガーマネジメントではこのように区別して行動を起こすことが大事なこととしています。
Well-being
マインドフルネスやアンガーマネジメントといった取り組みはストレスコーピングとしてだけではなく、Well-being(ただ単に健康な状態や心の病がない状態だけではなく、幸福な状態)やその人の生き方にも役立てられる効果的な取り組みです。
企業に関わる全ての人が、企業の生産性や業績の向上、人材・組織開発等に貢献しながら職場風土を改善し、そこで働く人たち自身も自発的、意識的ににストレスコーピングに取り組み、SOC・メンタルヘルスを向上させ、不調者を発現させないようにしていくことが、中小企業が目指すべき真のメンタルヘルスの取り組みではないかと思います。

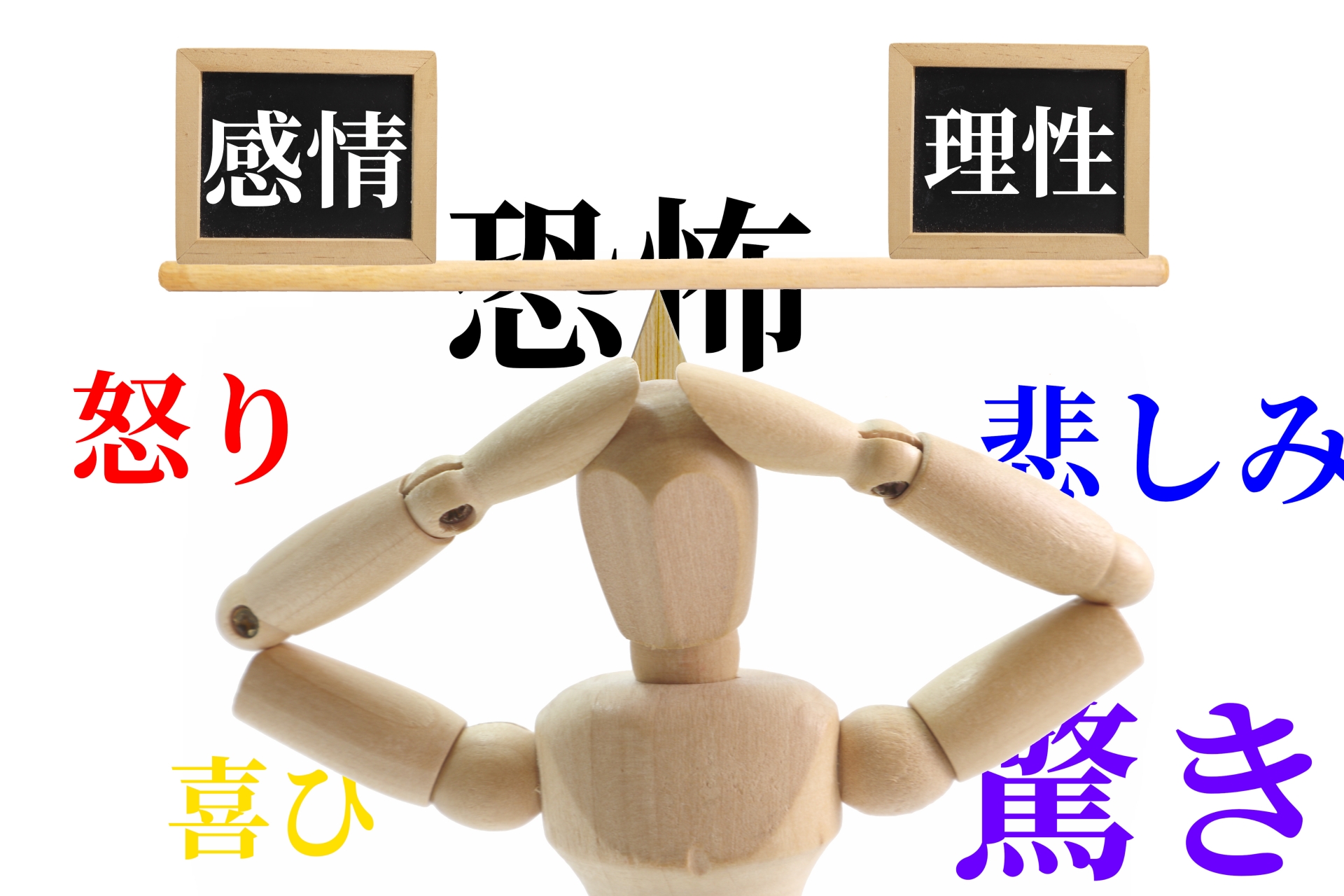
アンガーマネジメント
アンガーマネジメントは、このようなストレスに伴う「怒りの感情」や「行動」の背景にある認知に焦点を当て、自らの力で感情をコントロールできるようになることを目指した認知心理学の理論に基づいた方法です。
アンガーマネジメントでは怒ること自体は悪いことしてはいません。そもそも怒りとは私たちの身を守る大切な感情の一つだからです。アメリカの学者によって提唱されたものに動物の恐怖への反応で、「闘争・逃走反応」があります。これは危機や恐怖が差し迫ったとき、戦うか逃げるかとっさに判断して対応できる状態を作り出すことですが、人間も危機が迫ると、消化吸収や、体力回復に使うためのエネルギーを大腿筋や上腕筋などの大きな筋肉に回し、とっさの動作にも反応出来るように体を準備します。この時に使われるのが怒りの感情だといわれています。
アンガーマネジメントでは怒らなくなることではなく、怒る必要があるときは上手に怒れ、必要のないときは怒らなくて済むようになりましょうということを目指します。
アンガーマネジメントは手法であり、だれでも訓練すれば習得・習慣化できるものです。このことを理解してアンガーマネジメントを実践していきましょう。衝動、思考、行動をコントロールすることがポイントになります。

まず第一は衝動的に反射しないことです。例えば、朝の通勤の満員電車で言い合いや小競り合いのケースに出くわすことがありませんか。きっかけはちょっと足を踏まれたとか肘が当たったといった程度のもので、やり返したり、謝れと言ってもめたりするトラブルです。この時にすぐにカッとしてやり返したり、言い返したりしないことが大事です。怒りのピークは数秒といわれていますが、この数秒間に衝動的に反射しないことが重要なのです。そのためには、ひと呼吸つく、心の中で「大丈夫」とか「落ち着け」といった言葉をつぶやくことで怒りのピークをやり過ごし、少し冷静になって大きなトラブルになることを防ぎます。アンガーマネジメントでは怒りのピークをやりすごす方法は他にもいろいろありますが、色々覚えるのではなく、一つでいいので、いざというときに自分が自然に使えるものを習得しましょう。
また、怒りは突然沸き上がってくるものではなく、「不安」、「痛い」、「疲れた」、「寂しい」、「いやだ」といったネガティブな感情が私たちの中で膨れ上がって心のキャパシティーを超えたときに怒りの感情につながると言われています。つまり怒りとは第2次感情なのです。先ほどの通勤電車のケースではちょっとしたことで反射してしまう例を取り上げましたが、昨日上司に怒られたとか家で奥さんと喧嘩したとか様々なネガティブ感情が蓄積されているとちょっとしたことで、キャパシティーを超えてしまい、衝動的に反射してしまうのです。これを防ぐにはネガティブな感情をため込まないことも必要ですが、心のキャパシティーを大きくしていくことも必要です。

心のキャパシティーを大きくするには、その人が持っている思考(物事の考え方、捉え方、価値観など)を知ることが重要です。あなたにとって自分を怒らせる原因は何だと思いますか。それは誰かでしょうか、それとも何かの出来事でしょうか。実は誰かや出来事ではなく自分の思考に原因があるということです。自分の持っている思考、コアビリーフ(こうあるべきという思い)が目の前の現実と相いれないときに怒りの感情につながります。
職場で部下から上司に対して挨拶や報連相ができていないとか電車を待っている列に割り込んではいけないといった仕事上のあり方やマナーやルールは守るべきといったものまでさまざまなものがあります。
厄介なのは、信じているコアビリーフが人それぞれ違うということです。その人にとっては正解でも他の人ではそうでなかったり、程度が違ったりすることです。例えば会議の時間は守るべきだと考えている人達がいたときに、少なくとも5分前には会議室にいるべきという人もいれば時間ちょうどにいればいいという人もいます。お互いに思っている程度が違えば、人間関係にも影響が出るかもしれません。それではこのコアビリーフとどう付き合っていけばいいのでしょうか。自分の中で許せる領域、まあ許せる領域(ここまでが許容範囲)、許せない領域があったときに私たちが怒るのは許せない領域にあるものです。それ以外は怒る必要がないのです。怒ってしまった後によく考えると怒る必要はなかったなと後悔する場合はそれが許容範囲であったのかもしれません。必要なことには怒れて、必要のないことには怒らなくなるには、この許容範囲と許せない範囲の境界線を意識することと許容範囲をできるだけ広げてあげて、許せない範囲を減らしてあげることです。無理に広げる必要はないですが、できるだけ広げてあげたら境界線を安定化させることも必要です。その時々の機嫌で境界線を変えてしまうと周りが混乱します。そして境界線を安定させることに加えて、開示することも意識しましょう。
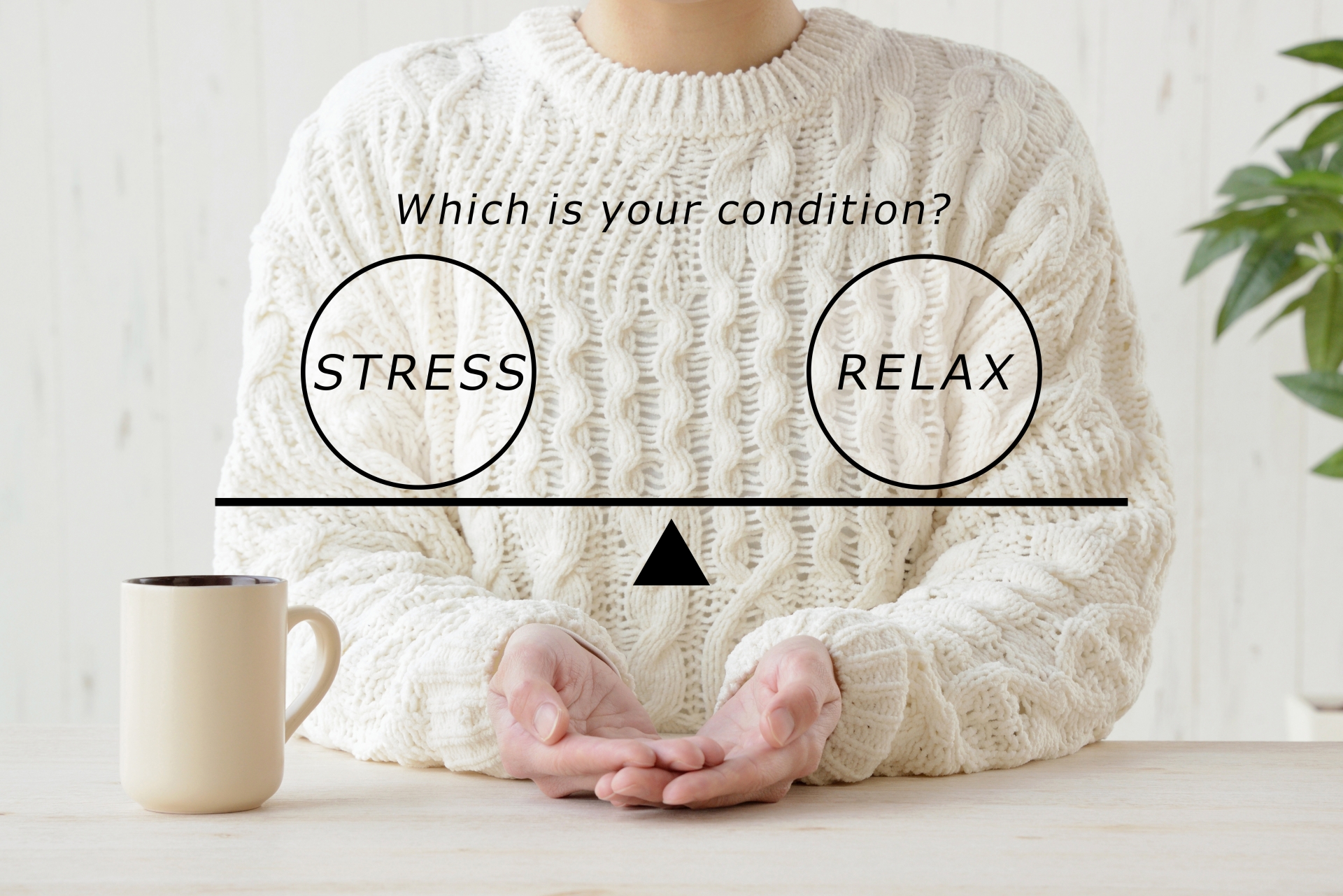
最後はコントロールできるものとそうでないものを区別して対処するというものです。例えば、悪天候や高速道路の渋滞など自分では変えることはできないことにイライラしたりしたことはありませんか。これはコントロールできないものをしようとしてイライラしているのです。コントロールできないものはまずは現実を受け止たうえで別の対処法を実践することです。雨が降ったら傘をさし、渋滞だったら音楽を聴いたり、誰かがいれば話をしたりして気分を変えます。変えられるものを変えようとしないということです。過去と他人は変えられないといいます。アンガーマネジメントではこのように区別して行動を起こすことが大事なこととしています。
Well-being
マインドフルネスやアンガーマネジメントといった取り組みはストレスコーピングとしてだけではなく、Well-being(ただ単に健康な状態や心の病がない状態だけではなく、幸福な状態)やその人の生き方にも役立てられる効果的な取り組みです。
企業に関わる全ての人が、企業の生産性や業績の向上、人材・組織開発等に貢献しながら職場風土を改善し、そこで働く人たち自身も自発的、意識的ににストレスコーピングに取り組み、SOC・メンタルヘルスを向上させ、不調者を発現させないようにしていくことが、中小企業が目指すべき真のメンタルヘルスの取り組みではないかと思います。