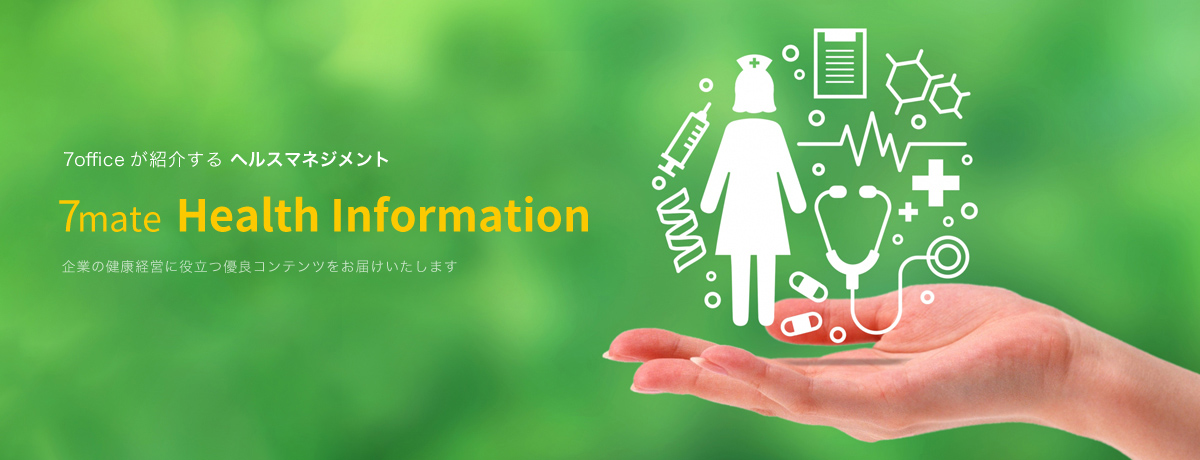第5回 マインドフルネス
前回はストレス対処能力を高める概念として首尾一貫感覚(sense of coherence:SOC)とこのSOCを高める企業の取組事例をご紹介しました。
今回は個人が取り組むストレスマネジメントの中で、SOCの向上につながる「マインドフルネス」と「アンガーマネジメント」を取り上げてみます。SOCを高める要素がいくつかある中で、特に「感情コントロール」「自己効力感」「人間関係」に効果があるといわれるのがこれら2つの手法です。

マインドフルネス
マインドフルネスは、仏教の瞑想や座禅をベースにマサチューセッツ大学のジョン・カバット=ジンによって1970年代にストレス低減の手法として確立されました。マインドフルネスの効果については科学的に実証されており、ゆっくりとした呼吸は副交感神経の働きを高め、これを意図的に調節すれば、心身をうまくリラックスさせられます。また、想像力を広げたり、集中力を高めたりという効果もあるといわれています。
私たちは普段町を歩いていたり、テレビを何気なく見ていたりする中でも、無意識に過去を思いだしたり、未来を想像したりと、心は時間時空をさまよっています。例えば、昨日上司に叱られたこと、明日気の進まないミーティングがあることなどあれこれ考えることで、心に負荷をかけているのです。特に自分ではコントロールできないことなら、なおさら無用なストレスを抱え込んでしまいます。
このようにあれこれと過去や未来に心がさまよっている状態をマインドワンダリングといって、簡単に言えば心ここにあらずの状態を指します。ある調査では日常の半分は「今」ではなく過去や未来を考えているそうです。このように常に何かを考えてしまうのは人間の特性とも言えます。実はこれらがストレスの大きな原因になっているといわれているのです。そのために心を過去や未来に飛ばさず現在にとどめおくのがストレスをため込まない方法なのです。「今」に意識を向ける。心ここにあらずの状態からハッと気づく、目覚めの状態に戻す。これを自在にこなす技法がマインドフルネスです。

ただ、今に集中するのは意外と難しいことですが、マインドフルネスは、訓練で誰でもできます。そしてその入り口は呼吸法です。意識的にゆっくりと呼吸をすると、その瞬間の身体に意識を集中できます。ヨガや太極拳のポーズやスローな動きも実は意識を身体につなぎ留めておくための工夫なのです。しかしどんなに頑張っても,いつの間にか余計なことを考えてしまいます。大切なのは、マインドワンダリングをやめようとすることではなく、そのことに気付くたびに心・意識を今に戻すことです。
マインドフルネスには集中力を高めるサマタ瞑想と想像力を広げていくヴィパッサナー瞑想の2つがあります。ここでは取り組みやすい瞑想としてサマタ瞑想の実践法をご紹介しましょう。
1.胡坐でも椅子に座ってでも結構です。背筋を伸ばしながらも身体の力が抜けている楽な姿勢をとります。
2.呼吸はゆったりと自然に任せてできるだけコントロールしないようにします。
3.鼻を通る空気の流れやお腹や胸の膨らみ、へこみ等の感覚を感じ取ります。
4.何かの雑念、考え、感情に気づいたら、ラベリング(雑念にラベルを貼って流すイメージ)して雑念、考えを切り上げて「今」に意識を戻します。
以上を最初は5分~10分くらい、慣れてきたら15分~30分程度やってみましょう。瞑想をしていると必ず雑念が出てきます。雑念は出てくるのが当然と考えましょう。大事なのはその雑念、考えに引っ張り込まれてしまわないことです。何か考えていることに気づいたら切り上げて今に戻ってくることが重要なのです。

マインドフルネス自体は、必ずしも心身への良い効果を期待するものではありませんが、結果的にストレスが減ったり、集中力が向上したりするので、日常生活を健康に送れるようになり、仕事の効率もアップします。ただし、重要なのは習慣化することです、継続的に実践し、自分の意識を観察する感覚を身につけることが肝心です。コントロールしようとするのではなく、結果的にうまくマネジメントされることが重要です。そのためには、今この瞬間を、価値判断することなく、能動的に観察するだけなのです。慣れてきたら座って瞑想する以外にも歩行中、食事中、入浴中などどこでもいつでもマインドフルネスの実践は可能です。ぜひマインドフルネスを生活の一部に取り入れていただきたいと思います。

今回は個人が取り組むストレスマネジメントの中で、SOCの向上につながる「マインドフルネス」と「アンガーマネジメント」を取り上げてみます。SOCを高める要素がいくつかある中で、特に「感情コントロール」「自己効力感」「人間関係」に効果があるといわれるのがこれら2つの手法です。

マインドフルネス
マインドフルネスは、仏教の瞑想や座禅をベースにマサチューセッツ大学のジョン・カバット=ジンによって1970年代にストレス低減の手法として確立されました。マインドフルネスの効果については科学的に実証されており、ゆっくりとした呼吸は副交感神経の働きを高め、これを意図的に調節すれば、心身をうまくリラックスさせられます。また、想像力を広げたり、集中力を高めたりという効果もあるといわれています。
私たちは普段町を歩いていたり、テレビを何気なく見ていたりする中でも、無意識に過去を思いだしたり、未来を想像したりと、心は時間時空をさまよっています。例えば、昨日上司に叱られたこと、明日気の進まないミーティングがあることなどあれこれ考えることで、心に負荷をかけているのです。特に自分ではコントロールできないことなら、なおさら無用なストレスを抱え込んでしまいます。
このようにあれこれと過去や未来に心がさまよっている状態をマインドワンダリングといって、簡単に言えば心ここにあらずの状態を指します。ある調査では日常の半分は「今」ではなく過去や未来を考えているそうです。このように常に何かを考えてしまうのは人間の特性とも言えます。実はこれらがストレスの大きな原因になっているといわれているのです。そのために心を過去や未来に飛ばさず現在にとどめおくのがストレスをため込まない方法なのです。「今」に意識を向ける。心ここにあらずの状態からハッと気づく、目覚めの状態に戻す。これを自在にこなす技法がマインドフルネスです。

ただ、今に集中するのは意外と難しいことですが、マインドフルネスは、訓練で誰でもできます。そしてその入り口は呼吸法です。意識的にゆっくりと呼吸をすると、その瞬間の身体に意識を集中できます。ヨガや太極拳のポーズやスローな動きも実は意識を身体につなぎ留めておくための工夫なのです。しかしどんなに頑張っても,いつの間にか余計なことを考えてしまいます。大切なのは、マインドワンダリングをやめようとすることではなく、そのことに気付くたびに心・意識を今に戻すことです。
マインドフルネスには集中力を高めるサマタ瞑想と想像力を広げていくヴィパッサナー瞑想の2つがあります。ここでは取り組みやすい瞑想としてサマタ瞑想の実践法をご紹介しましょう。
1.胡坐でも椅子に座ってでも結構です。背筋を伸ばしながらも身体の力が抜けている楽な姿勢をとります。
2.呼吸はゆったりと自然に任せてできるだけコントロールしないようにします。
3.鼻を通る空気の流れやお腹や胸の膨らみ、へこみ等の感覚を感じ取ります。
4.何かの雑念、考え、感情に気づいたら、ラベリング(雑念にラベルを貼って流すイメージ)して雑念、考えを切り上げて「今」に意識を戻します。
以上を最初は5分~10分くらい、慣れてきたら15分~30分程度やってみましょう。瞑想をしていると必ず雑念が出てきます。雑念は出てくるのが当然と考えましょう。大事なのはその雑念、考えに引っ張り込まれてしまわないことです。何か考えていることに気づいたら切り上げて今に戻ってくることが重要なのです。

マインドフルネス自体は、必ずしも心身への良い効果を期待するものではありませんが、結果的にストレスが減ったり、集中力が向上したりするので、日常生活を健康に送れるようになり、仕事の効率もアップします。ただし、重要なのは習慣化することです、継続的に実践し、自分の意識を観察する感覚を身につけることが肝心です。コントロールしようとするのではなく、結果的にうまくマネジメントされることが重要です。そのためには、今この瞬間を、価値判断することなく、能動的に観察するだけなのです。慣れてきたら座って瞑想する以外にも歩行中、食事中、入浴中などどこでもいつでもマインドフルネスの実践は可能です。ぜひマインドフルネスを生活の一部に取り入れていただきたいと思います。