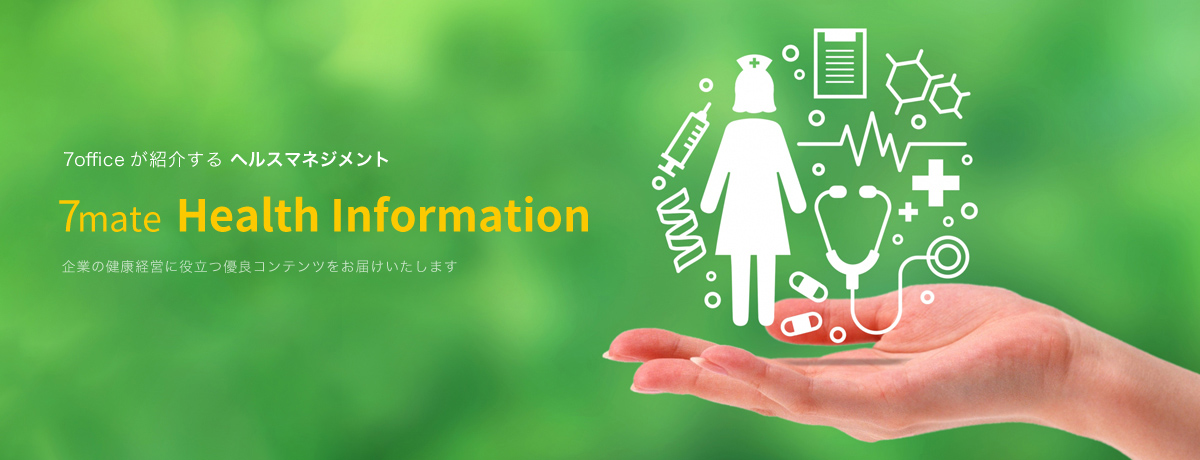第3回 首尾一貫感覚・・・培えてますか?
首尾一貫感覚とは
前回までお伝えした
 0次予防のための組織開発として、組織の効果性と健康性を高め、また組織が環境変化にタイミングよく適応していくために、組織を動かしている人の価値観や態度、風土、人と人との関係などをより良い方向に変革を図っていくことが大切です。
0次予防のための組織開発として、組織の効果性と健康性を高め、また組織が環境変化にタイミングよく適応していくために、組織を動かしている人の価値観や態度、風土、人と人との関係などをより良い方向に変革を図っていくことが大切です。
ここで0次予防を考えるうえで、参考になる概念をご紹介しましょう。
職場のストレス状況を踏まえた対策を考える上で重要な概念の1つとして首尾一貫感覚(sense of coherence:SOC)が挙げられます。SOCは、様々な身の回りの出来事に対し、ある程度予想でき、どのようなものか理解できるという「把握可能感(わかる感)」、なんとかなる・なんとかやっていけるという「処理可能感(できる感)」、自分にとって 意義ある挑戦とみなせる「有意味感(やるぞ感)」の3つから構成されており、ストレスの対処能力を測る指標として注目されています。
SOCとは自分の生きている世界が「首尾一貫しているという確信の感覚・筋道が通っている、腑に落ちるという感覚」です。自分や日々の生活の出来事を仮に自分では不本意であったとしても「まあ、しょうがないな」 「まあ、いいか」と納得して受け入れられる感覚のことです。そしてそういう出来事に対して「これには何らかの意味があり、なんとかなるに違いない」という確信を持つこととも言えます。
SOCは、持って生まれた素質や性格ではなく、その人の生き方や物事の受け止め方、向き合い方、関わり方、志向性などに大きく影響され、生まれてから後天的に獲得される感覚とされています。そして職場における様々な研究において、このSOCはメンタルヘルスの悪化を防ぐ方向に働くことが報告されており、社員のSOCが上がれば、心身の健康も保たれ、企業の生産性の向上や成長につながると考えられます。
さらに、SOC向上につながる主な要素として「仕事上の喜びや誇り・自由裁量度・仕事の複雑さ・価値観の共有」がありますが、これらを満たす職場環境や仕事の取り組みがSOCを向上させると言えます。
では次回、具体的にどのような仕事の取り組みが、SOCの向上に効果があったのか、一つ事例をご紹介したいと思います。

前回までお伝えした

 0次予防のための組織開発として、組織の効果性と健康性を高め、また組織が環境変化にタイミングよく適応していくために、組織を動かしている人の価値観や態度、風土、人と人との関係などをより良い方向に変革を図っていくことが大切です。
0次予防のための組織開発として、組織の効果性と健康性を高め、また組織が環境変化にタイミングよく適応していくために、組織を動かしている人の価値観や態度、風土、人と人との関係などをより良い方向に変革を図っていくことが大切です。ここで0次予防を考えるうえで、参考になる概念をご紹介しましょう。
職場のストレス状況を踏まえた対策を考える上で重要な概念の1つとして首尾一貫感覚(sense of coherence:SOC)が挙げられます。SOCは、様々な身の回りの出来事に対し、ある程度予想でき、どのようなものか理解できるという「把握可能感(わかる感)」、なんとかなる・なんとかやっていけるという「処理可能感(できる感)」、自分にとって 意義ある挑戦とみなせる「有意味感(やるぞ感)」の3つから構成されており、ストレスの対処能力を測る指標として注目されています。
SOCとは自分の生きている世界が「首尾一貫しているという確信の感覚・筋道が通っている、腑に落ちるという感覚」です。自分や日々の生活の出来事を仮に自分では不本意であったとしても「まあ、しょうがないな」 「まあ、いいか」と納得して受け入れられる感覚のことです。そしてそういう出来事に対して「これには何らかの意味があり、なんとかなるに違いない」という確信を持つこととも言えます。
SOCは、持って生まれた素質や性格ではなく、その人の生き方や物事の受け止め方、向き合い方、関わり方、志向性などに大きく影響され、生まれてから後天的に獲得される感覚とされています。そして職場における様々な研究において、このSOCはメンタルヘルスの悪化を防ぐ方向に働くことが報告されており、社員のSOCが上がれば、心身の健康も保たれ、企業の生産性の向上や成長につながると考えられます。
さらに、SOC向上につながる主な要素として「仕事上の喜びや誇り・自由裁量度・仕事の複雑さ・価値観の共有」がありますが、これらを満たす職場環境や仕事の取り組みがSOCを向上させると言えます。
では次回、具体的にどのような仕事の取り組みが、SOCの向上に効果があったのか、一つ事例をご紹介したいと思います。